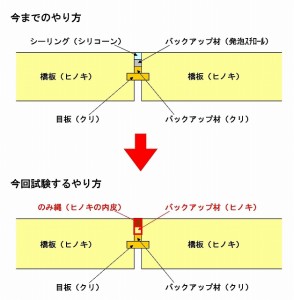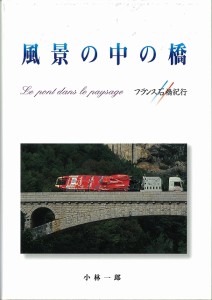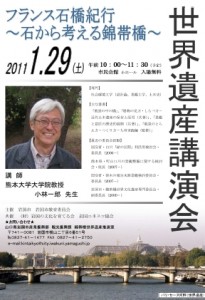1月30日午前、
前日夜から雪が降ったり止んだりの天候で、
実施が危ぶまれましたが、
無事、のみ縄充填が実施されました。
今までのシーリングより、見栄えは随分良いようです。
また、天然由来ですから、環境にも良いでしょう。
しかしこの先のみ縄は、数多くの試練を迎えることになります。
まず、現地で過酷な自然と人の靴にさらされ、その機能と耐久性を問われます。
ほかにも、目に見えないハードルもあります。
「のみ縄」の需要が昔に比べて低くなっていることから
通常、伐採されたヒノキを製材する過程で「のみ縄」
を取るようなことはしません。
すっかり省略されているこの作業をお願いしたとして、
一体どのくらい手間と費用がかかるのか
といったことも、確認しなければなりません。
美観そして機能性・耐久性、環境への負荷、
メンテナンスの容易性やその頻度、
それら全てを含めた上でのコスト面などなど
現代の要求を高い次元で両立させた方法が
「次の錦帯橋」には求められるのです。
1月29日に岩国市民会館小ホールで開催いたしました
世界遺産講演会に170名の方に参加いただきました。
本当にありがとうございました。
今回は、岩国ユネスコ協会の御協力で、
フレッシュな高校生の運営で、実に清々しいイベントとなりました。
小林先生のユーモアを交えたお話は、とてもわかりやすく、
まさに大成功でした。
小林先生の感想はこちら↓
http://gdp1.civil.kumamoto-u.ac.jp/hp/blog/index.php?id=683
そんな小林先生から著書をいただきました。
「風景の中の橋 ?フランス石橋紀行?」です↓
興味のある方、中央図書館に置いております。
(お問合せ先 中央図書館 電話0827-31-0046)
で、肝心の内容ですが、後日動画を配信する予定です。
御期待下さい。
「フランス石橋紀行 ?石から考える錦帯橋?」
第2回錦帯橋国際シンポジウム開催から
あまり時間が経っていないのですが、
2011年1月29日(土)午前10時から
岩国市民会館小ホールにおいて
世界遺産講演会を開催いたします。
講演会のチラシはこちら↓
チラシPDF→世界遺産講演会チラシPDF
熊本大学大学院教授の小林一郎先生は
第1回錦帯橋国際シンポジウムにおいて、
フランスのミシェル・コット先生、
アメリカのエリック・デロニー先生を
岩国にお招きする際に、お力添えいただき、
あわせて、パネルディスカッションコーディネーターとして
大いに会場を盛り上げていただきました。
また、先日の第2回錦帯橋国際シンポジウムにおいても、
パネリストとして、大変力強い言葉をいただきました。
「橋としては新しい錦帯橋の持つ価値とは、
330年余りにわたって受け継がれている
橋を架ける技術そのもので、
目に見えないところにある。
そこに、世界遺産登録するだけの価値がある。」
さて、今回はどのようなお話になるのでしょうか。
タイトルからは想像つきませんが、とても楽しみです。
当日の様子を動画配信いたします。
第1部 基調講演はこちら↓
http://gallery.inet.city.iwakuni.yamaguchi.jp/vod/vod_play.php?CNTID=4577
第2部 パネルディスカッションはこちら↓
http://gallery.inet.city.iwakuni.yamaguchi.jp/vod/vod_play.php?CNTID=4566
なお、まだ作業に着手していないのですが、
後日内容を報告書というで文書にします。